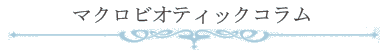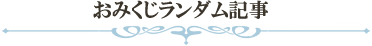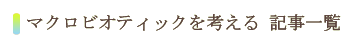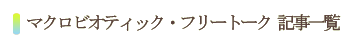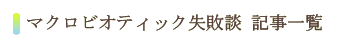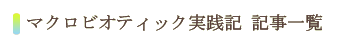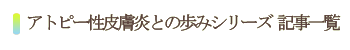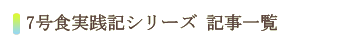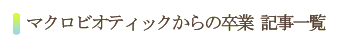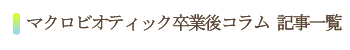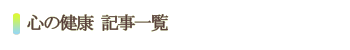春の風が吹き抜ける丘の上。花もほとんど散ってしまった桜の木の下に、優子は沈んだ顔をして腰を下ろした。膝を抱えてため息をつく。
優子は大学四年生だった。絵描きになる夢があった。けれどどうしても、作品が世に認められないのだった。コンテストに応募して結果を見るたびに、優子の自信は崩れていった。こうなったら就職するしかなかった。絵に関係する仕事に就こうといくつか会社を当たったが、どこも書類選考で落とされた。
この就職難の時代、もう、絵にこだわっている場合ではないのだろうか。私は、私の抱いた夢をどうしたら良いのだろうか。
ここで人生を終えられたら楽だろうな。暗い思いがよぎった。こんなはずではなかった。在学中に才能が開花し、誰かに目をつけられて、なんとか絵描きとしてやっていける。そんな未来を思い描いていたのに。
「どうしたんだ、そんなつまらない顔をして」
突然の声に優子は身を固くし、隣を見上げた。ニッと笑ったのは、黒縁メガネをかけた老人。枯れ木のように痩せた体にくたびれた白いシャツをまとって、足はサンダル履きだ。
考え事をするためにわざわざひとけのない場所を選んだのに、とんだ邪魔が入ったものだ。優子は小さく笑顔を作って会釈し、立ち上がろうとした。それを制するように、老人が隣にどっかとあぐらをかいて座り込む。
「お前さん、腹が減っているんじゃないかね」
顔を引きつらせながら黙って首を横に振る優子に、老人は竹の皮の包みを取り出す。
「ほら、玄米にぎりだよ。これでも食べなさい」
受け取らずにいると、老人はにこにこしながら竹の皮をむいた。ごま塩がまぶされた、こがね色した小ぶりのおにぎりが姿をあらわす。
「元気が出ないときはね、玄米飯を食べるんだよ。よく噛んで。そしたら、玄米がお前さんを励ましてくれる」
何を言っているんだろう、この人は。思いながらも、おにぎりを受け取り、軽くお辞儀をする。
老人は、納得したように大きくうなずいた。
「人生には、思うようにいかないことだってあるさ。苦しくてたまらないときもある。でもそこで投げちゃだめだ。いいかい、すべては動いているんだ。お前さんの状況も、必ず変わる。ほら、この桜の木を見てごらん」
幹を撫でながら、老人は桜の木を見上げた。
「誰に教えられなくたって、花が咲き、花が散り、若葉が出て、茂ってゆくだろう。そして少しずつこの木も大きくなっていく。そんなもんさ。一時期の状況だけ見て、判断しちゃいけない。
この桜も、冬になれば葉を落とすだろう。春に芽吹くためには、そんな時間も必要なのさ。お前さん、今、辛いんだろう? 大丈夫さ。きれいな花咲かすために力を蓄えていると考えればいい。ほらどうだい、太陽が、桜を生かすために照っているだろう。お前さんにもあの光が降り注いでいる」
優子も、老人につられるように桜を見上げた。わずかに残っていた花びらが、風に吹かれて舞い落ちる。
「信じることだ。お前さんが生きている、この大きな自然界の力を。落ち着いて、耳をすませてよく聞いてごらん。心の奥から、お前さんの命の声が聞こえないかい。その通りに動いてみるんだよ。頭でごちゃごちゃ考えずに、心が動く方へ、自然に動いてごらん。信じるんだ。きっとうまくいく。お前さんを生んだこの宇宙は、決してお前さんを見捨てたりしないさ」
視線を戻したとき、優子の目の前に老人の姿はなかった。
驚いて辺りを見回すが、人影はない。
優子は思わず立ち上がり、木の後ろをのぞき込んだりして老人を探した。だが、どこにもいない。
……どこに行ってしまったのだろう? 幻のようにかき消えてしまった。
木々の葉が、気持ちよさそうに風にそよいでいる。
気の抜けたようにその場に座り込んだ優子は、手元に残されたおにぎりを見つめた。そのおにぎりだけが、老人と優子を結んでいた。
おそるおそる、小さく、一口囓ってみる。
--元気が出ないときはね、玄米飯を食べるんだよ。よく噛んで--
老人の声が蘇る。優子は、米粒を奥歯でかみしめた。何度も、何度も。
かすかに甘い味が、唾液に混ざって口の中に広がる。
なぜだか涙が出て、優子は目をこすった。
家に帰って、もう一度、どこか良さそうな会社はないか探してみよう。今度の公募展に向けて描いていた絵も途中だった。明日、授業もあるし……。まずは卒業を目指さなきゃいけないんだった。
残りのおにぎりを食べきって、指についていたごま塩をなめる。いつの間にか日は傾き、空は夕暮れに染まり始めていた。
優子は立って、ジーンズのお尻を払った。
まっすぐ前を向いて、振り返ることなく、歩き出す。